| ほんとうにあった世界の美しい話 (講談社 1963) 総目次と関連リンク |
国会図書館 (こっかいとしょかん) で利用者登録 (りようしゃとうろく) をすると、オンラインで読 (よ) めます。

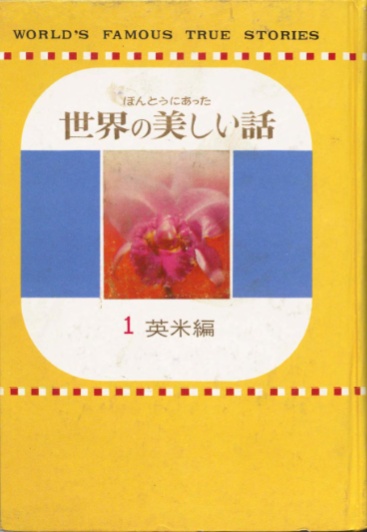 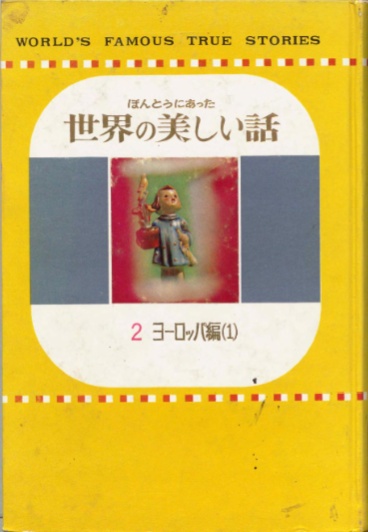 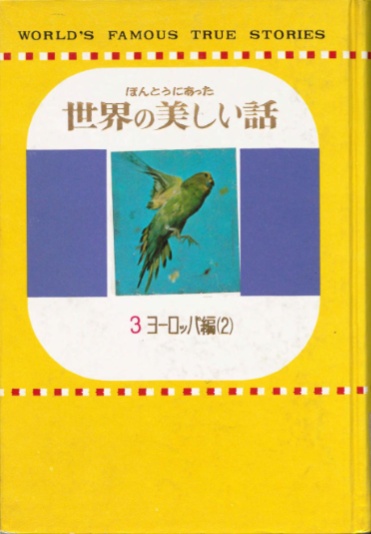 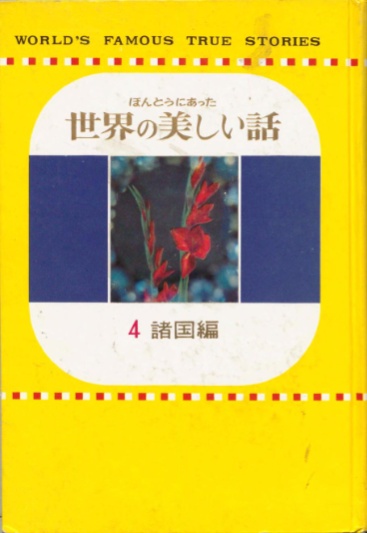 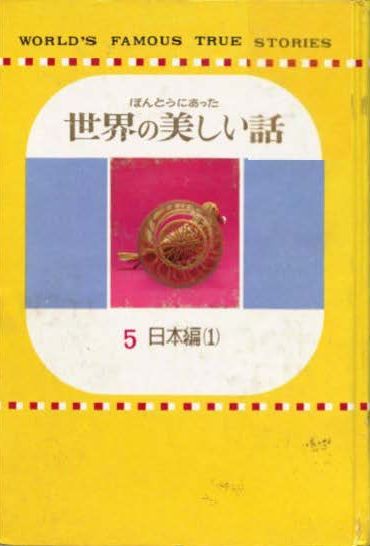 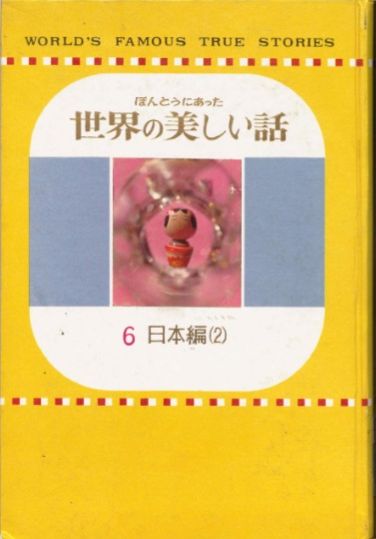 |
||
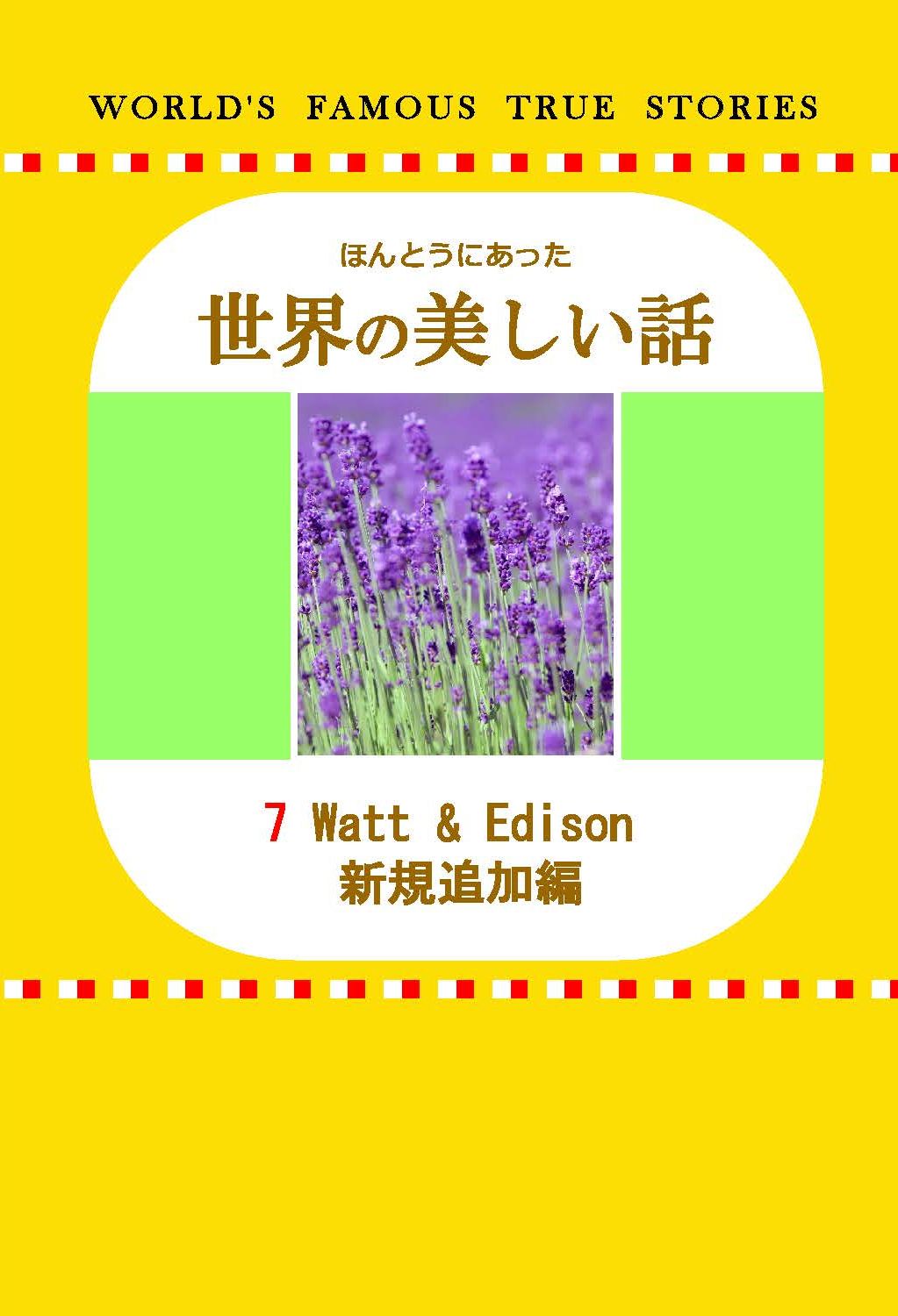 |
たくさんの少年を立ち直らせ、少年たちから心の親と慕われたおまわりさん 故 森田和雄 巡査部長(警視庁 八王子 諏訪派出所) の感動的な話を、 Watt & Edison 管理人が編集中です。 (2023年6月22日) (参考資料) 池田克彦 元警視総監 日本経済新聞 2018年9月5日夕刊 「明日への話題:隠れた功績」 朝日新聞 1990年10月28日朝刊 社会面 「ツッパリたちの心の親」 |
|
| ↓ Wikipediaなどの参考サイト | ||
| 1.英米編 https://dl.ndl.go.jp/pid/1627476/1/1 | ||
| 愛の人リンカーン | エーブラハム=リンカーン | Abraham Lincoln |
| 戦場からわが子への手紙 | ヒュー=ロフチング | Hugh Lofting |
| 灯台もりの少女 | グレース=ダーリング | Grace Darling |
| しんせつを売る店 | ジョン=ワナメーカー | John Wanamaker |
| 先生、ありがとう | ヘレン=ケラー | Helen Keller |
| エスキモーのなかよし | ウィルフレッド=グレンフェル | Wilfred Grenfell |
| あっ、あぶない! | トマス=エジソン | Thomas Edison |
| あの町をすくえ | トマス=ジャガー | Thomas Jaggar |
| くんしょうをもらった看護婦さん | ドロシー=トマス | Dorothy Louise Thomas |
| カナダの警察犬ナンバーワン | デール | “Dale,” Canada’s First Police Dog |
| けっしてまいったといわない少年 | ウィンストン=チャーチル | Winston Churchill |
| 大草原の友情 | セオドア=ワルデック | Theodore J Waldeck (1894 - c.1969) |
| うっかり大学者 | アイザック=ニュートン | Isaac Newton |
| インディアンの王女のま心 | ポカホンタス / ジョン=スミス | Pocahontas / John Smith (explorer) |
| 空をとぶお医者さん | ジョン=フリン | John Flynn (minister) |
| ランプを持った天使 | フローレンス=ナイチンゲール | Florence Nightingale |
| 愛のライオンがり | デービド=リビングストン | David Livingstone |
| なかよしきょうだい | ウィルパー / オービル=ライト | Wright Brothers |
| ついに九かいめに成功! | エドワード=ウィンパー | Edward Whymper |
| 南極のスコット | ロバート=スコット | Robert Scott |
| 親子二代で作った世界一のつり橋 | ジョン / ワシントン=ロープリング | John Roebling / Washington Roebling |
| つばさよ、あれがパリだ | チャールズ=リンドバーグ | Charles Lindbergh |
| 美しい大きなゆめ | ウォルト=ディズニー | Walt Disney |
| おかあさんのおかげで | ウィルマ=ルドルフ | Wilma Rudolph |
| 南北戦争のかげに | フランク / ウィリー 兄弟 | |
| 2.ヨーロッパ編(1) https://dl.ndl.go.jp/pid/1627477/1/1 | ||
| アルプスの名犬 | バリー(サンベルナール/セントバーナード犬) | Barry (dog) |
| ほんとうの友だち | ダモンとフィジアス(ローマ時代) | Damon and Pythias |
| コンチキ号の大冒険 | トール=ハイエルダール | Thor Heyerdahl |
| 苦しみを越えて | ルートヴィヒ=ヴァン=ベートーヴェン | Ludwig van Beethoven |
| ガラスのかけらをひろってあるく人 | ヨハン=ペスタロッチ | Johann Pestalozzi |
| ローランのつのぶえ | ローラン(シャルル大帝の家来) | Roland |
| やさしいエーリヒ | エーリヒ=ケストナー | Erich Kästner |
| オランダをすくった子ども | ハンス少年(オランダ) | Hans Brinker or The Silver Skates |
| コロンブスのたまご | コロンブス | Christopher Columbus |
| ボーランドの土を | マリー=キュリー | Maria Salomea Skłodowska-Curie |
| シベリアの少女 | ブラスコヴィア=ルポロヴァ | Praskovya Grigorievna Lupolova |
| 本件に関する文献・情報は主にロシア語であり、情報が極めて限られているので以下に補足します。 ロシア語のWikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/Луполова,_Прасковья_Григорьевна からの抄訳(大平陽一氏による) プラスコヴィヤ・グリゴリエヴナ・ルポロヴァ(1784年頃―1809年)は、イシムの流刑囚の娘で、19世紀西欧およびロシアの作家たちによる一連の作品の元型。世界の文化史では、エリザヴェタ・シビリャチカ、パラーシャ・シビリャチカ(パラーシャは「プラスコヴィヤ」の愛称形、シビリャチカには「シベリア娘」の意味がある)という名で知られている。 文化の中の痕跡 ルポロヴァの道徳的偉業は、ロシアだけでなくヨーロッパ諸国の文学芸術に広く取上げられた。フランスの閨秀作家マリー=ソフィー・コッタンは、自作の長編小説『エリザヴェタ、あるいはシベリアの流刑囚たち』(1806年、露訳初版1807年)のヒロインにルポロヴァを据えたし、イタリアの作曲家ドニゼッティはロマンティックな歌劇《2時間で8ヶ月、あるいはシベリアの流刑囚》(1827年5月13日、ナポリ、テアトロ・ヌオヴォで初演)を作曲した。 ルポロヴァの物語は、フランスのグザヴィエ・ド・メーストルも取り上げている。彼の中編小説『シベリアの少女』(1825年)はロシア語に訳され、『若いシベリア娘』(1840年)や『パラーシャ・ルパロヴァ』(1845年)の題名で刊行された。ド・メーストルの作品がA. S. プーシキンの『大尉の娘』に影響を及ぼした可能性は(道徳的軋轢、娘の検診というテーマ、権力者の慈悲の類似性からして)排除しきれない。19世紀後半には、匿名の作者による長編小説(時代設定を『大尉の娘』エと同時期のカテリーナ2世の治世に遡って移動させている)『パラーシャ・ルパロヴァ』が現れたが、この作品ではルポロヴァの経歴が、マーシャ・ミローノワの、物語と組み合わされている。ロシアの演劇において、ルポロヴァのイメージを具現化したものには、N. A. ポレヴォイの戯曲『シベリアの少女 パラーシャ』1840年1月17日アレクサンドリンスキー劇場で初演)がある。1840年には D. Iu. ストゥルイスキーが、同じ題名の自作のリブレットに基づいて、歌劇《シベリアの少女、パラーシャ》を作曲している。 正教への信仰が失われたことにより、20世紀の20年代以降パラーシャ・シビリャチカの名は長らくロシア史からぬぐい去られたままであったが、ロシアに大きな精神的・道徳的変化の到来を告げた新しい世紀の始まりと時を同じゅうして、その名も復活した。 2004年イシムに、彫刻家 V. M. クルィコフの手になるルポロヴァの記念碑が建立され、その台座には「世界に娘の愛の偉業をあらわしたプラスコヴィヤ・ルポロヴァに捧ぐ」という碑文が刻まれていた。2008年には、ペテルブルグ・ドキュメンタリー映画スタジオ《Kinor》で、K. V. アルチュホフ監督・T. P. サフチェンコワ脚本の映画《パラーシャ・シビリャチカ》が撮影されている。 参考 https://ja.wikipedia.org/wiki/グザヴィエ・ド・メーストル |
||
| 世界を一つの旗のもとに | ピエール=ド=クーベルタン | Pierre de Coubertin |
| 大だるの中の学者 | ジオゲネス(ディオゲネス) | Diogenes |
| 狂犬病とのたたかい | ルイ=パスツール | Louis Pasteur |
| 金色にかがやくスプーン | ウェルナー=ジーメンス | Werner von Siemens |
| 一つの大陸をむぶ電波 | グーリエルモ=マルコーニ | Guglielmo Marconi |
| だれも知らない海峡 | フェルディナンド=マゼラン | Ferdinand Magellan |
| 死のさばくをよこぎる | スベン=ヘディジ | Sven Hedin |
| 焼き肉さん、おやすみ | ジャン=ジャック=ルソー | Jean-Jacques Rousseau |
| 敵をだいじにした艦長 | フェリックス=フォン=ルックネル | Felix Luckner |
| 愛のしらべ | クララーシューマン | Clara Schumann |
| 国のためにつくした子どもたち | ノルウェーの子どもたち | |
| 星をめざして | コンスタンチン=ツィオルコフスキー | Konstantin Tsiolkovsky |
| なりふりかまわずに | アンリ=ファーブル | Jean-Henri Fabre |
| 愛の学校のマリア先生 | マリア=モンテッソリ | Maria Montessori |
| 3.ヨーロッパ編(2) https://dl.ndl.go.jp/pid/1627478/1/1 | ||
| ジャングルの中の病院 | アルベルト=シュバイツァー | Albert Schweitzer |
| 地底の探検 | Pierre Saint-Martin System caves, France-Spain |
|
| 星への道をひらいた人 | コンスタンチン=ツィオルコフスキー / ヴェルナー=フォン=ブラウン |
Konstantin Tsiolkovsky / Wernher von Braun |
| アルプスにきえたガイド | エドワード=ウィンパー「アルブス登頂記」 | Edward Whymper |
| 北極の海にちった友情 | ロアール=アムンセンアムンセン / ウンベルト=ノビレ |
Roald Amundsen / Umberto Nobile |
| 母うずら | イワン=ツルゲーネフ「猟人日記」 | Ivan Turgenev |
| 二つの海をつないだ苦心 | フェルジナン=ド=レセップス | Ferdinand de Lesseps |
| どろぼうにたべものをあげた人 | アッシジのフランチェスコ | Francis of Assisii |
| 祖国のために | ジャンヌ=ダルク | Jeanne d'Arc |
| ポンペイの名犬 | チトー少年 / ビンボ(犬) | Tito and his dog Bimbo |
| カレーの市民 | ウスターシュ=ド=サン=ピエールなど6人 | The Burghers of Calais |
| 目の見えない人へのおくりもの | ルイ=ブライユ | Louis Braille |
| なかのわるい、いい友だち | ダヴィンチとミケランジェロ | Leonardo da Vinci / Michelangelo Buonarroti |
| 赤十字の父 | ジャン=アンリ・デュナン | Henri Dunant |
| あらしの中のヘリコプター救助隊 | Norwegian ship Dovrefjelt on 3rd February, after she had run aground in the Pentland Firth |
|
| りつばなゆいごん | アルフレッド=ノーベル | Alfred Nobel |
| 姉の声 | フランソワ=オーギュスト=ロダン | Auguste Rodin |
| アルプスの少年鼓手 | ||
| 世界をすくった決死隊 | アイネル=スキナーランド(Einar Skinnarland) | ノルスク・ハイドロ重水工場破壊工作 リューカン=ノトデンの産業遺産 |
| 白鳥号と少年 | ||
| ミレーのはっぷん | ジャン=フランソワ=ミレー | Jean-François Millet |
| 少年の日のゆめに生きる | ハインリヒ=シュリーマン | Heinrich Schliemann |
| みにくいあひるの子 | ハンス=クリスチャン=アンデルセン | Hans Christian Andersen |
| 五年間のおくりもの | ジャン=ルナール / パセール=モール | |
| 人間はなによりも強い | ユーリイ=ガガーリン | Yurii Gagarin |
| 4.諸国編 https://dl.ndl.go.jp/pid/1627479/1/1 | ||
| シャカの教え | 釈迦 | 釈迦 |
| やくそくのカフスボタン | メイ=ランファン | 梅蘭芳 |
| アラスカのふぶきをついて | ウグルーク / イビーク | |
| ジンギスカンとたか | ジンギスカン | James Baldwin |
| 先生の写真をかざって | 魯迅 | 魯迅 |
| アフリカのガールスカウト | マンチェ=マセムラ | |
| 自由と独立のたたかい | シモン=ボリバール | Simón Bolívar |
| 大きなさばくをこえて | 玄奘法師 | 玄奘法師 |
| タゴールと鳥 | ラビンドラナート=タゴール | Rabindranath Tagore |
| わたしはあきらめない | ラジョロ | |
| ぞうのめかたをはかった少年 | 曹沖 | 曹沖 |
| 死海のたから | ダイブ/ムサ/トレバー博士 | |
| 美しい師弟愛 | 孔子 / 顔回 | 顔回 |
| よわいものの味方 | マハトマ=ガンジー | Mohandas Karamchand Gandhi |
| ふるさとのことばを聞いたぞう | ロンドン動物園 | |
| つりがね裁判 | 陳襄 | 陳襄 |
| ふたりの小さな英雄 | コンゴ(ヤリクサ) | |
| どろ人形と孫文少年 | 孫文 | 孫文 |
| 韓信のまたくぐり | 韓信 | 韓信 |
| チベットの少年シェルパの献身 | タイガー=カブ | John Baptist Lucius Noel |
| ろうやからのおくりもの | ジャワハルラール=ネルー(ネール) | Jawaharlal Nehru |
| 小鳥と遊ぶ少年 | 李白 | 李白 |
| 弓を射ない弓の名人 | ||
| かめわり温公 | 司馬光 | 司馬光 |
| わざわいの川をよろこびの川に | ||
| 5.日本編(1) https://dl.ndl.go.jp/pid/1627480/1/1 | ||
| ひみつの国にもぐりこむ | 川口慧海 | |
| 日本人小泉八雲 | 小泉八雲 | |
| 男にまけずに | 紫式部 | |
| 少年大工の決心 | 豊田佐吉 | |
| 富士山とのたたかい | 野中至 | |
| 大雪の日のお客さま | 佐野源左衛門 / 北条時頼 | |
| それは、めいしんだ | 福澤諭吉 | |
| ことばこそ心の道 | 金田一京助 | |
| みなしごの母 | 光明皇后 | |
| 赤シャツの少年 | 宮沢賢治 | |
| 知多半島を走る水 | 久野庄太郎 | |
| しんせつだったアメリカ人 | 浜田彦蔵 | |
| たこをあげたおとな | 河村瑞賢 | |
| 川原の石合戦 | 竹千代(徳川家康) | |
| 苦心、また苦心のすえに | 酒井田喜三右衛門 | |
| 貧民街のともしび | 徳永恕(ゆき) | |
| 小説に命をかけて | 滝沢馬琴 | |
| 横綱をことわったおすもうさん | 雷電為右衛門 | |
| 友情のメダル | 西田修平 / 大江季雄 | |
| 先駆者の苦心 | 前野良沢 / 杉田玄白 | |
| ローマへいった少年使節 | 天正遣欧少年使節 | |
| マントをぬいだ学生 | 河上肇 / 田中正造 | |
| 祖国日本をすくえ | 伊藤博文 / 井上馨 | |
| ああ、ベンゲット道路 | 太田恭三郎 | |
| タロ・ジロは生きていた | タロ / ジロ | |
| 6.日本編(2) https://dl.ndl.go.jp/pid/1627481/1/1 | ||
| 行こう、緑の大地へ | 安田恭輔(フランク安田) | |
| 小さな動画の王さま | 大藤信郎 | |
| 十和田湖に生きる | 和井内貞行 | |
| 北のはての大冒険 | 間宮林蔵 | |
| 村田銃の発明 | 村田経芳 | |
| 三本の矢 | 毛利元就 | |
| 日韓友情のかけ橋 | 曽田嘉伊智 | |
| 半年かかってうつした字書 | 勝海舟 | |
| 雪の日の大名行列 | 渡辺崋山 | |
| 山をくりぬいて | 友野与右衛門(重之) | |
| あばらやの大画家 | 葛飾北斎 | |
| ふしぎな糸 | 井上でん | |
| お国のために どれいになって | 大伴部博麻 | |
| 地図つくり十八年 | 伊能忠敬 | |
| おみやげのはまぐり | 野中兼山 | |
| 海をわたってきたぞう | ||
| 三人の少年船乗り | 乙吉(音吉) / 久吉 / 岩吉 | |
| 三つのたから | 一休(宗純) | |
| 美しい空の勇者 | 淵上百合子 (当時の新聞 1960.7) |
NORTHWEST AIRLINES, INC., DOUGLAS DC-70, N 292, NEAR MANILA, PHILIPPINE ISLANDS, JULY 14, 1960 Accident investigation report completed and information captured Date: Thursday 14 July 1960 |
| 少年よ、大志をもて | ウィリアム=スミス=クラーク | |
| マーカス島の気象観測班 | 田口龍造ほか | |
| 谷をまうおりづる | 竹川和夫 | |
| 風をきるオートバイ | 本田宗一郎 | |
| ほのおの中のアナウンサー | 丹羽国夫 | |
| すえこざさ | 牧野富太郎 | |
このページの先頭に